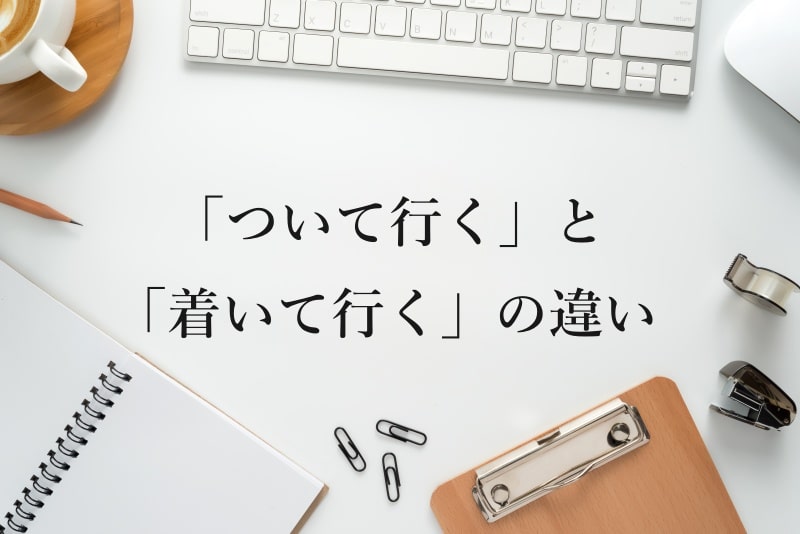「ついて行く」と「着いて行く」。
ひらがなと漢字、この2つの表現を正しく使い分けることはできますか?
どちらも誰かと一緒に移動する際に使われますが、実は微妙な違いがあります。
「ついて行く」は同行することを、「着いて行く」は目的地に到達することを意味し、使い分けを間違えると誤解を招くことも。
本記事では、それぞれの意味や適切な使用場面を詳しく解説し、例文を交えてわかりやすく紹介します。ぜひ最後まで読んで、正しい使い分けをマスターしましょう!
「ついて行く」と「着いて行く」の基本的な意味

「ついて行く」の意味と使い方
「ついて行く」は、誰かの後を追う、または指示や方針に従って行動することを意味します。具体的には以下のような場面で使われます。
- 友人と一緒に買い物に行く際に「私もついて行くよ」と言う。
- 会社の方針に「ついて行く」ことで、チームワークを保つ。
- 師匠や指導者の教えに従う意味で「師匠について行く」。
- 新しい環境に慣れるために、先輩について行く。
- トレンドや流行について行くことで、最新の情報を得る。
- 新しい技術について行くために、セミナーに参加する。
- 運動を始めた際に、インストラクターについて行くことで継続する。
- ビジネスの場面で成功している人について行くことで、学ぶ機会を増やす。
- 旅行中に迷わないように、ツアーガイドについて行く。
「着いて行く」の意味と使い方
「着いて行く」は、目的地に到達することを強調した表現です。「ついて行く」と似ていますが、「着く」という漢字を用いることで到着の意味が加わります。
- 「駅まで着いて行く」:目的地である駅に一緒に到着する。
- 「友達の家まで着いて行く」:友人の家に行き、そこに到達する。
- 「学校まで着いて行く」:生徒が先生と一緒に学校へ到着する。
- 「イベント会場まで着いて行く」:友人と一緒にイベントの開催場所に到着する。
- 「目的地まで着いて行く」:ナビゲーションを頼りに、指定された場所に到達する。
- 「登山の際に山頂まで着いて行く」:グループで一緒に頂上を目指す。
- 「海外出張で現地オフィスまで着いて行く」:同僚と一緒に目的地へ向かう。
- 「飛行機で目的地に着いて行く」:長距離移動の際に、グループで一緒に目的地に到達する。
- 「観光ツアーでガイドについて行きながら目的地に着いて行く」:目的地に安全に到着する。
両者の漢字表記の紹介
「ついて行く」はひらがなで書かれることが多く、文脈によって「着いて行く」と漢字表記が使われることもあります。「つく」の意味を明確にするために、文脈に応じて適切な漢字表記を選びましょう。
「着いて行く」は「到着する」という意味を持ち、目的地がある場合に適した表記です。一方、「ついて行く」は単に同行することを示すため、目的地の有無に関わらず使用できます。
そのため、文章を書く際には、目的地が明示されているかどうかを確認し、適切な漢字表記を選ぶといいですね。
「ついて行く」と「着いて行く」の使い分け

使用場面の違い
- 「ついて行く」は、行動を共にすることに重点を置く。
- 「着いて行く」は、目的地に到達することを意識する。
- 「ついて行く」は、人物や思想に対しても使用される。
- 「着いて行く」は、物理的な場所に対して限定的に使われる。
- 「ついて行く」は、抽象的な概念に対しても使える(例:流行について行く)。
- 「着いて行く」は、具体的な地理的な移動に重点がある(例:駅まで着いて行く)。
- 「ついて行く」は、精神的・文化的な場面でも使われる(例:師匠の教えについて行く)。
- 「着いて行く」は、実際の移動や到着を示す(例:目的地まで着いて行く)。
ニュアンスの違い
「ついて行く」は、物理的な移動だけでなく、思想的・精神的な従属の意味も持ちます。一方、「着いて行く」は物理的な移動に焦点を当てた表現です。
- 「ついて行く」は、時間をかけて変化していく状況にも適用される。
- 「着いて行く」は、比較的短時間で到達できる目的地に適用される。
- 「ついて行く」は、関係性の持続を示すことができる(例:上司の指導について行く)。
- 「着いて行く」は、一時的な移動に限定されることが多い(例:友人の家まで着いて行く)。
- 「ついて行く」は、ペースを合わせる意味も持つ(例:話について行くのが大変だ)。
- 「着いて行く」は、単に目的地に到達する意味で使われる(例:目的地に着いて行く)。
- 「ついて行く」は、努力や順応を伴うニュアンスを持つ(例:新しい環境について行く)。
その際の目的地の解説
「着いて行く」は、目的地を明示することが多い表現です。「ついて行く」には目的地が明確でなくても使用されることがあります。
- 「ついて行く」は、具体的な目的地がなくても使用可能(例:先生の考えについて行く)。
- 「着いて行く」は、物理的な目的地が必ず存在する(例:レストランまで着いて行く)。
- 「ついて行く」は、途中で変化する状況にも適用できる(例:時代の流れについて行く)。
- 「着いて行く」は、明確なゴールを前提とする(例:山頂まで着いて行く)。
- 「ついて行く」は、精神的なフォローアップにも使える(例:リーダーについて行く)。
- 「着いて行く」は、最終的な到達を示す(例:目的地に着いて行く)。
「ついて行く」と「着いて行く」の例文

日常での使用例
- 「友達の後をついて行く。」(同行する意味)
- 「レストランまで着いて行く。」(到着を含む)
- 「犬が飼い主の後をついて行く。」(忠誠心や愛着を示す)
- 「新しい環境になれるために、先輩について行く。」(学びながら適応する)
- 「流行について行くのが大変だ。」(時代の変化に適応する)
- 「子供が母親について行く。」(安心感を得るための行動)
学校や仕事での使用例
- 「上司の指示について行く。」(従う)
- 「新しい職場に着いて行く。」(到達)
- 「先生の話について行くのが難しい。」(理解が追いつかない状況)
- 「リーダーの考え方について行く。」(思想や方針に従う)
- 「会議での議論について行くために、事前に資料を読む。」(準備をすることで追いつく)
- 「プロジェクトの方針について行く。」(計画の流れに沿う)
特定の状況における使用例
- 「先輩のアドバイスについて行く。」(従う)
- 「登山グループに着いて行く。」(目的地へ同行)
- 「海外出張で現地スタッフについて行く。」(仕事のサポートを受けながら移動)
- 「スポーツの試合でコーチの指示について行く。」(戦略を理解して実行)
- 「友人が引っ越し先を決めるのについて行く。」(決定に伴って行動)
- 「新しい趣味に挑戦するために、先輩について行く。」(経験者のサポートを受ける)
「ついて行く」や「着いて行く」と似た表現

「同行する」との違い
「同行する」はフォーマルな表現で、どちらの意味にも使えますが、特に「着いて行く」に近いです。また、「同行する」は書き言葉としてよく使われ、公的な文書やビジネスシーンで目にすることが多いです。
- 「社長の海外出張に同行する。」(フォーマルな表現)
- 「患者の通院に家族が同行する。」(支援の意味を持つ)
- 「観光ツアーでガイドに同行する。」(目的地へ一緒に移動する)
一方、「ついて行く」は日常的な表現であり、友人同士やカジュアルな会話で用いられることが多いです。
「従う」との違い
「従う」は思想や指示に従う意味であり、「ついて行く」と似ていますが、移動の意味は薄れます。「従う」は上下関係を強調することがあり、命令や規則を守るというニュアンスを含みます。
- 「会社の方針に従う。」(規則に沿う)
- 「先生の指導に従う。」(教育の場面で使われる)
- 「警察の指示に従う。」(法律や権威に従う場面)
「ついて行く」は必ずしも上下関係を示すわけではなく、同じ立場の人同士でも使用されます。
- 「友達について行く。」(同行の意味)
- 「先輩のアドバイスについて行く。」(尊敬は含むが、従属ではない)
「追従する」との違い
「追従する」は主にネガティブな意味で用いられ、無批判に誰かの行動をまねる意味があります。「追従する」は自分の意志がなく、他人の言動を盲目的に模倣するという否定的なニュアンスを持ちます。
- 「権力者に追従するだけの政治家。」(批判的な意味)
- 「世間の流行に追従するのではなく、自分のスタイルを貫く。」(対比的な使い方)
- 「上司の意見にただ追従する部下。」(自分の意見がないことを批判する表現)
「ついて行く」は、主体性を持って行動する場合にも使えるため、必ずしもネガティブな意味にはなりません。
- 「尊敬する人について行く。」(自発的な行動)
- 「新しい技術について行くために勉強する。」(適応するための努力)
「着いて行く」の派生的な使い方

到着を表す言い回し
「着いて行く」は「目的地に到着する」ことを明示する際に便利です。この表現は、相手と同じ目的地へ向かうことを強調するため、会話の中で目的地を明確に示したい場合に適しています。
- 「彼と一緒に空港まで着いて行く」
- 「先生の案内で美術館まで着いて行く」
- 「迷わず会場まで着いて行くことができた」
また、「着いて行く」は目的地を示すだけでなく、ある場所へ同行する際の意思決定の強さを示すこともあります。
比喩的な表現
「着いて行く」は、「成功まで着いて行く」などの比喩表現でも使われます。単なる物理的な移動だけでなく、ある目標や概念に向かって進んでいくことを意味する場面でも用いられます。
- 「理想の人生へ着いて行くために努力する」
- 「彼の哲学に着いて行くことができるかどうか」
- 「夢を追いかけながらゴールまで着いて行く」
このように、比喩的な意味では「成功」「目標」「目的」といった概念と組み合わせて使われることが多く、前向きな意味合いを持つことが特徴です。
日常の言葉としての使用
日常会話では「ついて行く」の方がよく使われますが、状況に応じて「着いて行く」も適切に使い分けましょう。「着いて行く」は特に、相手と同じ場所に到達することを強調する際に便利です。
- 「イベントの集合場所まで着いて行く」
- 「彼女が先に行ったので、後から着いて行く」
- 「初めての場所なので、友達に着いて行くことにした」
また、日常的な会話では「着いて行く」が「ついて行く」と混同されやすいため、文脈に注意することで、より正確な意味を伝えることができます。
「一生ついていく」とは

その表現の背景
「一生ついていく」は、忠誠や信頼を示す言葉です。
この表現は、特定の人物や組織、理念に対して強い忠誠心を持ち、最後まで共に歩むという決意を示します。特に、師弟関係やスポーツチーム、会社組織などでよく使われますね。
この表現が生まれた背景には、日本の伝統的な価値観である「忠義」や「恩義を大切にする」文化があります。
かつての武士道や職人の世界では、一度仕えた主君や師匠に対して、生涯をかけて仕えることが美徳とされました。この考え方が、現代の「一生ついていく」という表現にも影響を与えていると考えられます。
感情や意義
「あなたについて行きます!」のように、強い意志を表します。
この言葉には、単なる同行という意味を超えて、相手に対する尊敬や信頼、決意が込められています。ビジネスの場面では「この会社に一生ついて行くつもりです」と言うことで、組織への忠誠心や継続的な貢献の意思を示すことができます。
また、人間関係においても、「あなたに一生ついて行きます」と言うことで、パートナーや恩師に対する強い信頼を表現することができます。恋愛関係では「一生ついて行くよ」と誓うことで、結婚や長期的な関係への決意を伝える場面もあるでしょう。
この表現を使う際には、相手に対する敬意と、実際にその決意を実行する覚悟が必要です。軽々しく使うと、信頼を損なう可能性があるため、場面に応じた適切な使い方を心掛けましょう。
例文による解説
- 「このチームに一生ついて行く!」(スポーツチームへの忠誠)
- 「師匠に一生ついて行くつもりです。」(職人や芸術の分野で師弟関係を大切にする場面)
- 「親友として、どんなことがあっても一生ついて行くよ!」(友情の誓い)
- 「この会社の理念に共感したので、一生ついて行く覚悟です。」(ビジネスの場面)
- 「あなたと結婚して、一生ついて行きます。」(恋愛・結婚の場面)
- 「家族を支えるために、一生ついて行く覚悟だ。」(家庭内の決意)
このように、「一生ついて行く」はさまざまな場面で使われ、忠誠心や決意を示す強い言葉として機能します。
辞書での探し方

辞書の利用方法
辞書を活用することで、単語の正しい意味や使い方を深く理解することができます。「つく」という動詞の語源や成り立ちを調べる際には、以下のポイントに注意すると良いでしょう。
- 「つく」の語源や意味を調べる。
- 類義語と使い分けを確認する。
- 漢字表記(着く、付く、就く、突く など)の違いを理解する。
- 実際の用例を辞書で確認し、使用場面を比較する。
- 古典的な使用例があれば、歴史的な意味の変遷を学ぶ。
- 言葉の派生語や関連語を調べ、表現の幅を広げる。
語源と成り立ち
「つく」は、動作の継続や到達を表す意味を持ちます。この動詞は、日本語の中で非常に多くの使い方をされており、文脈によって意味が異なります。
- 「着く」:到達する(例:「目的地に着く」)
- 「付く」:くっつく(例:「泥が靴に付く」)
- 「就く」:職務や役職に就く(例:「社長の座に就く」)
- 「突く」:押し出す、攻撃する(例:「槍で敵を突く」)
これらの違いを意識しながら、辞書で調べると理解が深まります。
類義語探しのコツ
類義語との違いを意識して学習すると、表現の幅が広がります。辞書で類義語を調べる際には、次のポイントを押さえると効果的です。
- 「ついて行く」と似た表現(同行する、従う、追従する など)を確認する。
- それぞれの語のニュアンスや使われる場面を比較する。
- 例文を辞書から引用し、自分でも使ってみる。
- 英語辞典を活用し、英語の表現と対比してみる。
- 語源辞典を参照し、言葉の成り立ちを学ぶ。
このように、辞書を活用することで、単語の正確な意味や適切な使い方を身につけることができます。